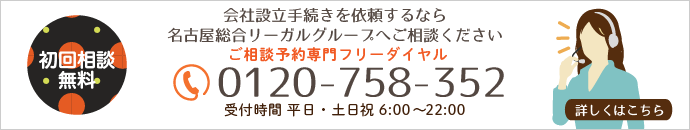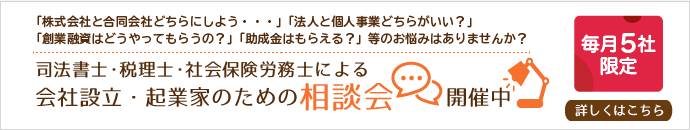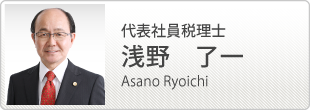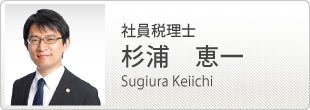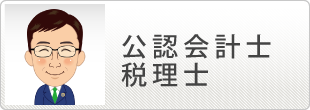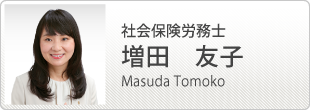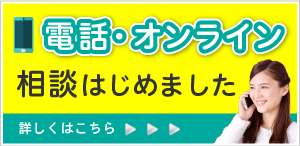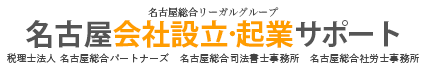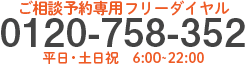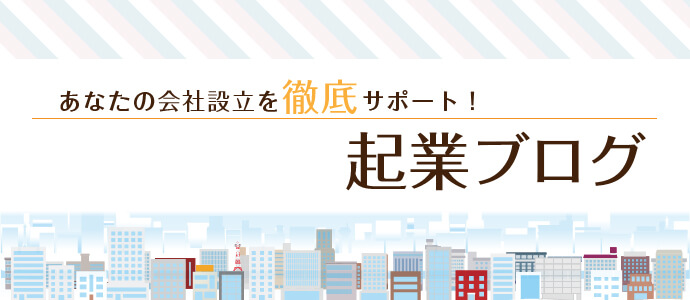
外国籍の方を雇い入れる際に年金制度で注意することは
※こちらの記事は2024年12月19日までの情報を元に作成しています。執筆時点以降の事情変更により記事の内容が正確でなくなる可能性がございます。
引用しているウェブサイトについても同様にご注意ください。
比較的規模の小さい会社様におかれましても、外国籍の方を採用することは日常的に行われるようになりました。近年の人不足、特にサービス業や小売業における人手不足感には深刻なものがあるようで、頭を悩ませている経営者の皆様も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
外国籍の方を採用される際に、確認しなければならないことに、まず就労可能な資格がある方なのかどうか、ということがあるかと思います。この点について、日本国籍の方を雇入れる際とは異なった視点が必要となり、留意される必要があります。厚生労働省のホームページにおいても注意喚起がなされています。 (https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/anteikyoku/gairou/980908gai01.htm)
人出不足を、業務の効率化によって解決することも、有効な方策でしょう。
今回ご案内する「中小企業省力化投資補助金」は、IoTやロボットといった省力化製品を導入することで、人手不足の解消を支援するものです。
さて、就労が認められる方であることが分かった後、就労条件を決めていくこととなりますが、 この際、社会保険に加入する否かという判断が必要になります。社会保険の加入の要否判断に際し、対象者の国籍は無関係ですので、あくまで日本国籍の方の採用時と同様の基準で判断する必要があります。
採用した外国籍の方が自社で社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入することになった場合に、確認されることをお勧めしたいことがあります。 それは、国民年金加入の未加入期間が発生していないかどうか、ということです。
採用された外国籍の方が、この度はじめて日本に入国し、はじめて社会保険に加入される場合、「入国から社会保険加入までの期間」は、国民年金の加入者となり、国民年金保険料を納付する義務があります。(但し、本国との社会保障協定等により、日本の年金制度の被保険者とならない方を除く)また、前職を離職されて今回、 社会保険に加入することとなった場合、離職から就職の間に空きがあれば、その間は、国民年金の加入者となり、国民年金保険料を納付する必要があります。
このように、国民年金加入者となるべき期間があるのにも関わらず、制度についての理解が不十分であるがために、国民年金加入手続きをしないままであったり、国民年金保険料を未納のままにしておかれますと、不測の事態が発生した場合(たとえば、障害年金の受給等)における年金給付や、在留資格許可に影響を及ぼす可能性があります。
出入国在留管理基本計画(出入国在留管理庁HP)
(https://www.moj.go.jp/isa/policies/policies/basic_plan.html)
外国籍の方を雇い入れ、社会保険に加入する必要のある場合には、会社様からも、国民年金加入期間においては国民年金保険料を納付する必要があることをご案内されるとよいでしょう。
こんな時は免除申請をご案内ください
1.初めて日本に入国された方の場合で、前年において日本で所得がない場合には、原則、初年度については、ご本人の申請により年金保険料の全額免除が認められるとされています。未納のまま放置することと、免除申請を行っておくことでは、年金納付記録上、全く異なる結果を生じさせることになります。
2.前の職場を退職して、社会保険資格喪失した後、失業保険を受けていた場合には、「失業特例免除制度」が利用出来る可能性があります。失業したことがわかる書類(雇用保険の離職票や資格喪失確認通知書など)を持参の上、住所地の市区町村役場で免除申請を行うことを検討してもよいでしょう。
国民年金の免除制度について 日本年金機構のホームページはこちら
(https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html#cmsshitsugyo)
-
最新の記事
- 健康保険証の廃止とマイナ保険証への移行
- 外国籍の方を雇い入れる際に年金制度で注意することは
- 中小企業省力化投資補助金のご案内
- 事業成功のために ~SWOT分析②
- 事業成功のために ~SWOT分析①
- 事業成功のために ~創業計画書の作成
- 「労働者協同組合」が設立できるようになります。
- 会社設立登記後に必要な手続きとは?
- 消費税インボイス制度導入に伴う起業への影響
- 支店の所在地における登記の廃止
- 合同会社の資本金
- 電子定款認証のテレビ電話方式と令和3年の改正
- LLPとは?
- 決算月はどうやって決めるの??
- 目的とは
- 『特例有限会社の商号変更による株式会社の設立登記』って何?
- 設立の際の定款認証、出資の履行と役員選任の順番
- 過去の申告書控えが見当たらない場合の対処法
- 平成31年税制改正後の法人の実効税率
- 会社設立をお考えの方が知っておかなければいけない消費税の本則課税と簡易課税
-
月別
- 2025年1月 (2)
- 2024年12月 (1)
- 2024年7月 (2)
- 2024年6月 (1)
- 2022年12月 (1)
- 2022年8月 (1)
- 2022年7月 (2)
- 2022年2月 (1)
- 2021年11月 (1)
- 2021年9月 (1)
- 2021年2月 (1)
- 2020年11月 (1)
- 2020年2月 (1)
- 2019年11月 (1)
- 2019年10月 (1)
- 2019年6月 (1)
- 2019年5月 (1)
- 2019年4月 (1)
- 2019年2月 (1)
- 2018年12月 (1)
- 2018年11月 (2)
- 2018年8月 (1)
- 2018年7月 (2)
- 2018年4月 (1)
- 2018年1月 (1)
- 2017年12月 (1)
- 2017年11月 (1)
- 2017年9月 (1)
- 2017年7月 (1)
- 2017年6月 (1)
- 2017年2月 (2)
- 2017年1月 (1)
- 2016年12月 (1)
- 2016年11月 (1)
- 2016年10月 (1)
- 2016年9月 (1)
- 2016年7月 (1)
- 2016年6月 (1)
- 2016年5月 (1)
- 2016年3月 (1)
- 2016年2月 (1)
- 2016年1月 (1)
- 2015年10月 (1)
- 2015年9月 (1)
- 2015年7月 (1)